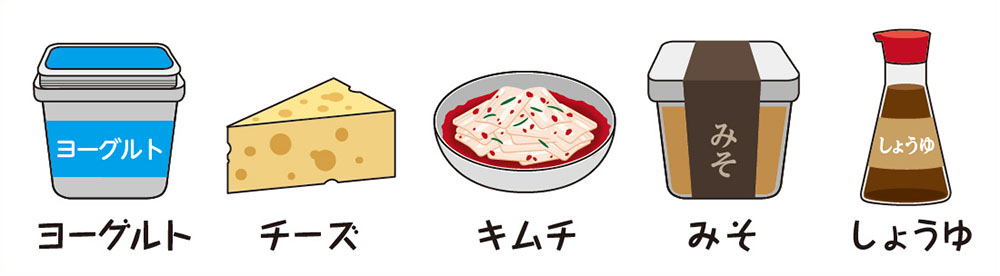もうすぐ七夕ですね♪
天の川をはさんで別れ別れになっている織姫と彦星。
2つの星が年に一度再会できる、ロマンチックな日として知られています。
今回はそんな夏の風物詩、七夕とその「行事食」についてご紹介します!
●七夕はどうやって誕生したの?
七夕は、中国と日本の風習・行事が結びついてできた節句の一つです。
例えば、学校や地域で集まって短冊に願い事を書き、笹竹に吊るした経験がある方も多いのではないでしょうか?実はこれ、中国のとある風習に由来があるのだとか。
「乞巧奠(きっこうでん)」とは?
織姫と彦星の伝説にあやかって、女性の裁縫の上達を願う「乞巧奠(きっこうでん)」という風習が中国にありました。これが奈良時代に日本に伝わり、宮中で広まったとされています。時代が進むにつれ、いろんな要素が乞巧奠に加わり、少しずつかたちがかわっていきます。江戸時代には民衆にも伝わり、書道の上達を願うことを中心として定着したそうです。そして現代では、様々な願い事をする行事となりました。
乞巧奠を含んだ中国の風習と、日本古来のけがれや災厄を祓う行事が結びついて、七夕が誕生したと言われています。
●願いがこもった行事食!七夕にはコレ!
季節の節目など特別な日に食べる料理のことを「行事食」と言います。お正月に食べるおせち料理や、ひな祭りに食べる菱餅などが有名ですね♪そんな行事食には家族の健康や幸せを願う意味があると言われているそうです。
七夕の行事食は夏にぴったりの「そうめん」です!なぜそうめんが七夕の行事食となったのか、その由来について調査しました。
そうめんは元々はお菓子だった!?
そうめんは中国から伝来したお菓子に由来すると言われ、これを「策餅(さくべい)」と呼びます。小麦粉と米の粉を練り、縄の形にしたものと推定されています。
中国の故事にみる 策餅(さくべい)と7月7日
これは大昔の中国でのお話。7月7日に亡くなったとある貴族の子供が、鬼となって熱病を流行らせました。困った人々が子供の好物だった策餅をお供えすると、祟りが静まったそうです。それ以来、7月7日に策餅をお供えすると病気にならない、と言い伝えられるようになったのだとか。
策餅(さくべい)から素麺(そうめん)へ
そんな「策餅(さくべい)」ですが、日本に伝わると「策麺(さくめん)」とも呼ばれるようになります。それが時を経て「素麺(そうめん)」になったと伝えられています。こうした流れがあって、七夕の行事食がそうめんになったというのが一つの説です。ちなみに、7月7日はそうめんの日とされているんですよ☆
●七夕の行事食!そうめん×カレー
七夕の誕生やそうめんの由来について知ったところで、そうめんをさらに美味しく食べるレシピをご紹介します♪
【 材料 1人分 】
- うどん用カレー (中辛or辛口) ・・・1袋 ※販売終了しました
- そうめん・・・1人分
- オクラ(トッピングにどうぞ)・・・1本
作り方はとっても簡単!
うどん用カレーをそのまま器に盛りつけ、ゆでたそうめんと絡めるだけ!
トッピングにゆでたオクラをのせると色鮮やかになりますよ♪
ピリリと辛い味が食欲をそそります(*^▽^*)
 ●七夕にぴったりの果物☆
●七夕にぴったりの果物☆
カレーの横に添えてある星形のもの、何かご存知ですか?
これは「スターフルーツ」という果物で、カットした断面が星形に見えることからこうした名前がつきました。南インドなど熱帯アジアが原産で、日本でも沖縄県や宮崎県で栽培されています。さっぱりとした味で夏の暑い日などにぴったりの果物ですよ♪
毎年何気なく迎えていた七夕には様々な歴史があったんですね。
今年はちょっと変わったそうめんレシピで、夏を元気に乗り切りましょう!